SNSのヘイト解消に効果的な「カウンタースピーチ」、どう使う?

特定の個人や集団に対する差別的言動「ヘイトスピーチ」は、社会と民主主義に対する脅威だ。米メタが投稿の「ファクトチェック機能」を廃止したことでヘイト増殖が懸念されるなか、スイス発の「カウンタースピーチ」に関する研究が注目を浴びている。どうすればヘイトを効果的に解消できるのか?

おすすめの記事
「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録
「ヘイトスピーチを拡散する人たちは、実にうまく連携している」。ジュネーブのフェミニスト財団「ジェンダー平等基金」の理事長を務めるアンヌ・セリーヌ・マシェ氏はこう話す。互いに口裏を合わせることで、負のエネルギーを増幅しているという。
ヘイトに関して同氏が特に危惧するのは、こうしたインターネット上の誹謗中傷による女性への悪影響だ。女性の政治家やジャーナリストがネット上で言葉の暴力にさらされれば、それを読む全ての女性も間接的に影響を受ける。女性は往々にしてあまり目立たないように、出しゃばらないようにとしつけられるため、次第に言論の場を避けるようになり、結果的に民主主義を脅かすことになりかねない。「実際にヘイトスピーチの標的となり、公から姿を消した人もいる」

ヘイトへの問題意識を高めることが強力な対策になる、とマシェ氏はみる。「ヘイトスピーチに対抗することは可能であると、はっきりさせなければならない」
ヘイトスピーチとは?
ヘイトスピーチとは、特定の人種、民族、宗教、性別などに属していることを理由に、個人や集団を侮辱したり、中傷したりする差別的言動を指す。
スイスの世論調査会社ソトモが実施した2022年の調査外部リンクによると、スイス国民の9割近くが、ネット上の言葉の暴力が「非常に蔓延している」または「ある程度蔓延している」と感じていた。だがこれはスイスに限った問題ではない。人種主義と不寛容に反対する欧州委員会(ECRI)外部リンクはヘイトスピーチを「民主主義社会の結束」をゆるがす「深刻な脅威」と捉え、こうした言動を無視すれば実社会での暴力や紛争を助長しかねないとした。
とりわけ今年は、ネット上の発言を巡り波乱の幕開けとなった。米メタは1月、フェイスブックとインスタグラムにおける表現の自由を尊重するため、第三者が投稿内容の事実関係を確認する「ファクトチェック」を米国で廃止すると発表し、物議を醸した。今後はヘイトスピーチについても対応を緩和するとして、ドナルド・トランプ大統領の2期就任前に歩調を合わせた。
わずか1%のアカウントが生むヘイト
デジタル世界を支配するのは、今やティックトック、フェイスブック、インスタグラムといった大規模SNSだ。だが今なら、小さなテコで効果的にヘイトスピーチを阻止できるかもしれない。その1つが、差別的な言動に積極的に対抗する「カウンタースピーチ」だ。
スイスのプロジェクト「ストップ・ヘイトスピーチ」によると、ネット上の差別発言の65%は、全オンラインアカウントの約1%が発信源だ。つまり憎悪に満ちた言動を発するのが一握りの人間なら、少人数で対抗できるはずだ。そのため「ストップ・ヘイトスピーチ」はワークショップなどで差別発言に対抗する方法を伝えている。その際、単に怒りをぶつけるのではなく、発言がヘイトスピーチであると示唆する方が効果的だという。

ヘイトスピーチは、一部刑罰の対象となる。例えば個人的な名誉毀損や、欧州連合(EU)加盟国の場合、昨年2月に全面施行されたデジタルサービス法(DSA)に反する内容などだ。しかし「ストップ・ヘイトスピーチ」の発起人ソフィ・アッハーマン氏は、法的な処罰だけではヘイトスピーチを撲滅できないと話す。
同プロジェクトが連邦工科大学チューリヒ校(ETHZ)と2021年に行った最初のフィールド実験外部リンクでも、同様の結果が出ている。それによると「オンライン上のヘイト増加に伴い、そうした投稿自体を減らす取り組みも行われてきた」が、政府やSNS企業が有害投稿を監視・削除する「コンテンツモデレーション」は価値ある発言も同時に制限し、ヘイトスピーチを「減らすより、むしろ増殖させる」可能性がある。そのため「国際機関や市民団体(中略)は対抗手段として、カウンタースピーチを用いる傾向が強まっている」。
これは既に2021年の時点で出された結論だ。あれから中央集権化や権威主義的な政府と企業との結びつきは更に強まった。X(旧ツイッター)のオーナー、イーロン・マスク氏は、インドのナレンドラ・モディ大統領の信奉者を自称するが、モディ氏自身も反イスラム的なヘイト発言外部リンクについて政敵などから非難されている。モディ政権下で報道の自由外部リンクが低下したインドでは、コンテンツモデレーションが抑圧の道具として悪用されかねない。
「共感」が効果的
前出のETHZのフィールド実験「SNSフィールド実験で分かった人種差別的なヘイトスピーチを減らす共感ベースのカウンタースピーチ」は公開されてから既に3万回以上閲覧された。科学論文としては異例の多さだ。
研究では、実在の人物と思われる英語版Xのプロフィールの中から、ヘイトスピーチ投稿を含むアカウントを千件以上観察した。実験用に作成した一部のアカウントでは、研究者らが他のアカウントのツイートにユーモアで対処し、発言が後難を呼ぶかもしれないと示唆したり、共感を促したりするなど、一貫して中立的で非政治的な立場を取った。
その結果、動物を使ったコミカルなミーム画像・動画や、自分のツイートが家族や雇用主などあらゆる人の目に触れる可能性を示唆するコメントは、全く効果がなかった。一方で、「アフリカ系アメリカ人にとって、そういう言葉を使っている人を見るのは本当に辛い」といった共感を促すコメントは効果があった。
全体的に「比較的小さいながら、一貫して効果があった」という。共感を促す書き込みを受けたアカウントは外国人に対する排他的なツイートが減った。投稿すること自体が減り、また元のヘイト投稿を削除するケースも多かった。
「言論の自由」推進派も納得のカウンタースピーチ
米テネシー州にあるバンダービルト大学の研究所「フリースピーチの未来」は、カウンタースピーチの使い方をまとめたガイドライン外部リンクの中でETHZの同研究を参考文献として推奨している。
コンテンツモデレーション反対派とは、言論の自由を尊重するために投稿内容の管理や制限に難色を示す人たちだ。興味深いことに、こうした反対派もカウンタースピーチの効果を認めている。同研究所のヤコブ・ムチャンガマ氏とナタリー・アルキヴィアドゥ氏は、カウンタースピーチに関する複数の論文をまとめた学術出版外部リンク(2023年)の中で、シリアやアフガニスタンなどの国々では、「コンテンツモデレーション」がヘイトスピーチを制限する一方で、政府幹部のプロパガンダや検閲を逃れるためにSNSを利用している反体制派にも悪影響を与えたと指摘。シリアの反体制派メンバーが内戦を記録した何千ものビデオがユーチューブの自動コンテンツモデレーションによって削除された例を挙げた。そしてカウンタースピーチこそがネット上のヘイトに対抗する唯一の方法だとした。
1カ月でコメント3万件
アッハーマン氏と「ストップ・ヘイトスピーチ」、並びに同氏が代表を務める財団「公共ディスコース基金」は現在、スイスの主要メディアと協力し、オンライン上のコメントを観察し、科学的な分析を進めている。1カ月で3万件ものコメントを投稿したアカウントに遭遇したときは、誰もが「絶対に人間業ではない」と思ったが、実在の人物によるものだったという。
こうして得られた経験値は、前出の「ジェンダー平等基金」など、ヘイトに狙い撃ちされる可能性のある人々とも共有している。「10万人のフォロワーを持つ政治家ではない人々のモチベーションも高めたい。ヘイトスピーチの65%の原因が1%なら、少人数で対抗できるはずだ」(アッハーマン氏)
被害者を救う「第三者」のコメント
「ストップ・ヘイトスピーチ」の活動の1つは、ヘイトスピーチの悪影響を最小限に抑える方法を被害者に伝えることだ。その際、被害者本人はカウンタースピーチを用いるべきではないという。ヘイトスピーチやその発信者と向き合う心理負担が不釣り合いに大きく、感情的になりやすいためだ。
「ストップ・ヘイトスピーチ」に触発されたドイツ人のカスパー・ヴァイマンさんは、チャットグループを使ってヘイトスピーチに対抗している。「カウンタースピーチを必要とする人がリンクを投稿すると、大勢のアーティストや文化関係者がコメント作成に協力してくれる」と話す。ヴァイマンさんは仲間と一緒に文化人を対象としたセミナーも行っており、業界のネットワークは更に広がっている。
「女性差別的なヘイトスピーチは自分でコメントするが、(トランスジェンダーの人々に対する不合理な恐怖や憎悪を込めた)トランスフォビア的な内容の場合、グループに投稿し、他のメンバーに協力を求める」。取材当日、ヴァイマンさんは「God is trans(神はトランスジェンダー)」と書かれた帽子をかぶっていた。
SNSは民主主義に必要

SNSは、背後に「信じられないほどの危険性をはらむ巨大企業」が潜むと同時に、「民主主義が躍動する社会交流の場」でもある。そのためヴァイマンさんにとって、ユーザーがこうしたプラットフォームからただ離れるのではなく、定着して有効に活用できることが重要だとした。
ヴァイマンさんは昨年ティックトックで3カ月の実験的プロジェクトを行った。男性優位思想のフィルターバブル(アルゴリズムで自分の好きな情報ばかりが表示される現象)に敢えて飛び込み、「男らしさ」を追求する投稿が女性差別的な内容になりかねない危険性を示した。何気ない発言がいかに人を傷つけるかを示し、見る人の感情に訴えるビデオは何百万回も視聴され、多数シェア外部リンクされた。
チャットグループの人数を尋ねると、すぐにスマートフォンを取り出し「(メッセージアプリの)ワッツアップで250人、シグナルで95人」と教えてくれた。たったこれだけの人数でも、カウンタースピーチでヘイトの矛を収められるのだ。

おすすめの記事
民主主義
編集:Mark Livingston、独語からの翻訳:シュミット一恵、校正:ムートゥ朋子

JTI基準に準拠












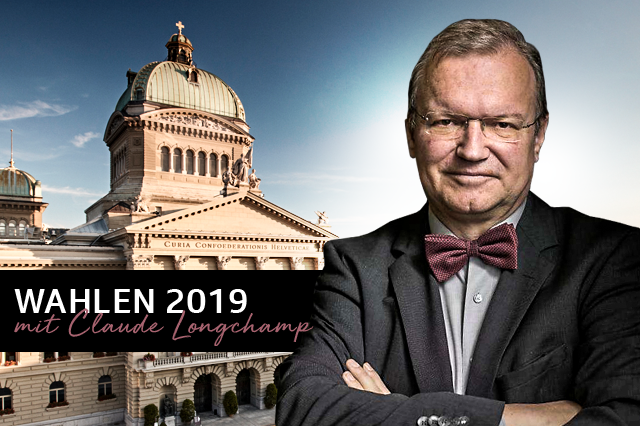
swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。