過疎化と戦うスイスの村 村おこしに知恵を絞る

船でしか行き来できないスイスの小さな村、クインテン。過疎化が進むこの村は今、生き残りをかけて様々な知恵を絞る。そんな中、地元の財団は独自の「子供の補助金制度」を導入した。
スイス東部ザンクト・ガレン州の自治体クアルテンに付随する村、クインテン外部リンクは「東スイスのリビエラ(海岸)」との異名をとる。日当たりの良いクーアフィルステンの斜面にはブドウの他に、温暖な気候を好むヤシの木、イチジク、キウイが育つ。
村の名前は、音楽の和音(テルツェンは3度、クアルテンは4度、クインテンは5度)とは関係ないようだ。スイス歴史百科事典とクインテン」によると、中世初期にクール教区の無名の農地(第3、第4、第5の土地)の数え方に由来するとされる。
しかし、この村も田舎ではよくある「老化」に悩まされている。村の住人は現在38人外部リンク、平均年齢は56歳だ。ボートか徒歩でのみアクセス可能で、辺境の保養地として知られている。
日当たりの良いヴァーレン湖の北岸は、チューリヒからわずか1時間でアクセスできる人気のスポットだ。ただクインテンの村民は、ちょっとした買い物でさえ湖を渡る船に依存する生活を送っている。
そこで村民は財団「Quinten lebt(クインテンは生きている)」を設立。若い家族を村に引き付けるべく、財団は独自の「子供の補助金制度」を打ち出した。
村の住民になると毎月200フラン(約2万2800円)が支給される。また、20歳以下の子供には1人当たり最大2万フラン財団から支給されるという。「今クインテンで暮らす子供は3人だけだ」と財団会長のジョエル・シュミット氏は言う。
学校の先生
「1960年には23人の子供が学校に通っていました」とマリアンネ・ギガーさんは振り返る。現在83歳のギガーさんは、村の生き字引だ。だが1973年には児童生徒数の減少を理由に閉校した。

1959年、当時22歳だったギガーさんは若き教師としてこの村にやって来た。そして今日までこの村に留まっている。漁師のアロイス・ギガーさんと結婚し、一緒に7人の子供を育てた。ギター教師としての資格も取った。「私たちの場合、子供の補助金はとても高額になっていたでしょうね」と笑う。
財団が推進するこのプロジェクトは評価するが、「ここでの冬に耐えられる人でなくては難しい」と強調する。インタビューにはドイツで外科医として働く息子のウルスさんも加わった。よく子供たちと一緒に両親の家で休暇を過ごすという。「でも冬の間中、ずっとここで一人きりで過ごすと考えただけで、気が滅入りますよ」
村に定着するには、しっかりと根を張り、家族や仕事といった役割が必要だという。「そして健康な人でなければ長続きしません」とウルスさんが付け加えた。「その点、母は教会の聖歌隊のメンバーです。教会ではオルガンを演奏し、夏になるとギフトショップの手伝いをし、ブドウ畑ではできることなら何でも手伝っています」
村を支える観光業
スイスでは数少ない「本当に車のない」この村を活性化させるため、財団が打ち出した妙案は他にもある。その1つが、蚕の養殖施設「お蚕ホテル」だ。主にブドウ栽培と観光業に支えられるクインテンだが、財団のおかげで村に養殖の運営に携わる雇用が3つ創出された。
7つの村で構成される自治体クアルテンは、観光業の上に成り立っている。エーリッヒ・ツォラー市長によると、雇用の2つに1つは直接的・間接的に観光業が関わっているという。目下にはヴァーレン湖が広がり、背後にはスキー場の整備がされた山を持つこの村は、チューリヒからも訪れやすい。
子供の補助金制度に対し、ツォラー市長は「これが本来の目的にかなっているかどうかは疑問だが、最終的に資金の使い道を決めるのは財団だ。もちろん市議会は、原則的に村おこしを支援したい考えだ」とコメントした。
自給自足の生活
マルグリット・ベアロッハーさんは、クインテンの村の中心部で暮らす。すぐ隣の空き家は、現在2世帯が入居できるアパートに改装中だ。幼少の頃から毎年、この祖父の家で夏休みと秋休みを過ごしたベアロッハーさんは、1983年にクインテンに移り住んだ。

自宅の地下室では、農産物を販売する。全て自分で栽培したり加工したりした物だ。今はちょうどジャムとシロップの瓶に貼るラベルを作っているところだ。「春から秋にかけて、庭やブドウ園の仕事が忙しくて手が離せません。そんな時、こうして冬の間に準備しておいた蓄えがあると本当に助かります」とベアロッハーさんは言う。
「隣の家に再び活気が戻って、家主さんに安定した収入が確保されれば嬉しいですね。1928年に私の母が初めてクインテンに越してきた当時から、ここは既に空き家でしたから」とベアロッハーさん。そしてお金が若い家族を引き付けるための適切な手段かは疑問だと言う。「それよりも理想を示すことの方が重要です」。なぜなら、人里離れたクインテンは特殊な生活環境であるため、ここで暮らしていくには、ある意味で信念が必要だからだ。
イベント開催で村の活性化に貢献
村の中心から少し離れたところに、ハンスペーター・カドナウさん(52)は暮らす。もちろん、湖の眺め付きだ。船で湖を渡れない期間が最も美しいと言うカドナウさんは、ブドウ園を営む傍ら希少種のマンガリッツァ豚と3頭のロバ「ピカソ、マラドーナ、ジャクソン」を飼育する。

スイス東部のグラウビュンデン出身のカドナウさんは、元々はトンネル建設業者だった。この村に来たのは単なる偶然だという。ここに住むようになって既に10年が過ぎた。「20歳だったらこの村には来ないね。しかし仕事柄、世界中の大都市の建設現場で色々な物を見てきたから、今はこの村で静かに過ごしたいんだ」。カドナウさんは、子供の補助金制度を高く評価している。「子どものいない村は死んだも同然ですよ」
カドナウさん自身も、クインテンにより多くの命を吹き込むことに貢献している。「私がここに来たとき、事実上、この村は死んでいました」と言うカドナウさん。今では春から秋にかけてブドウ園の真ん中に設置された野外ステージでコンサートやイベントを主催する。ここはレマン湖北岸のラヴォーにも負けない最高品質のワインの産地でもある。
「宿泊と朝食だけのB&B(ビー・アンド・ビー)を利用すれば、より多くの人がイベント後も足を留めることができる」とカドナウさんは言う。事実、B&Bは、財団が進めるもう1つの村おこし案でもある。現在、財団は実現化に向け、5部屋の宿泊施設付き飲食店の運営を担う借り手、又は住み込みできる家族、そしてコックを1人募集中だ。財団のシュミット会長は、子連れ家族が名乗りを挙げてくれることと、新たな雇用が3つ創出されることを期待している。
クインテンで導入した子供の補助金制度やB&Bは、スイスでは既に別の場所で同様のキャンペーンが実施されたことがある。ヴァレー(ヴァリス)州の小さな村、アルビーネンは、新しい住民を呼び込むために移住者1人当たり最大2万5千フランを提供すると約束した。
グラウビュンデン州のヴナ村では、財団が空き家を分散型のホテルとして利用。またティチーノ州のモンティ・ディ・シアガ村では、素朴な石造りの家が1フランで売りに出ている。但し、家の改装は買い手の負担だ。
新たに水上タクシー導入へ
その他にも、太陽エネルギーを利用した水上タクシーを導入するという案も出ている。ヴァーレン湖を渡る船に依存する生活は、村の一部の人々にとって悩みの種であるためだ。ちょうど実家に来ていた外科医のウルスさんも、船が定刻に対岸のムルクに到着しなかったせいで飛行機を逃した経験が何度もあると言う。「私が理解できないのは、国の許可を得て運航しているにも関わらず、電車の乗り継ぎが悪いことです」
それに対しヴァーレン湖の船舶運航の経営を担当するマルクス・シェラーさんは、2015年に導入された時刻表は、特に学童を対象に調整されていると反論する。「乗客が多い場合、遅延が生じる日もある。または船を2回出すこともある」。自治体のツォラー区長はまた、「クインテンの住民は優遇措置を受けている上、運賃も割安」と弁明した。
財団のシュミット会長によると、水上タクシーのプロジェクトは順調に進行しているという。確かなのは、既存の船舶運航と競合するのが目的ではないということだ。「水上タクシーは補足的な移動手段という位置づけです。ヴァーレン湖の船舶運航も、この新しい経営ユニットに統合されます」と会長は説明する。
前出の元教師、ギガーさんはこのプロジェクトに賛成だ。しかし、一つ気に入らないことがあるという。それは船の時刻表が列車の時刻表と一致していないことだ。
自治体との確執
しかし財団はなぜ、これら数々のプロジェクトを立ち上げたのか?「政治はあてになりません。自治体は何もしてくれませんから」とシュミット会長。クインテンは湖の対岸と比べ、ないがしろにされていると会長は不満を漏らす。ウルスさんもそれに賛同して言う。「自治区全体で最も多く税金を支払う住民が暮らしているのが、ここククインテンです。対岸では一体どれだけの税金が自治体に流れ込んでいるのか見てみたいものです。それなのに対岸の地方行政にとって、ここは単なる無人地帯に過ぎないのです!」
もちろんツォラー区長はそれに反論し、自治区はクインテンの支援に色々な面で貢献していると言う。郵便配達や廃棄物処理に加え、数多く訪れる観光客のために公衆トイレも建設した。「他にも数え出したらきりがありませんよ…」
▼クインテン村のレポート映像(スイスドイツ語)
(独語からの翻訳・シュミット一恵)

JTI基準に準拠










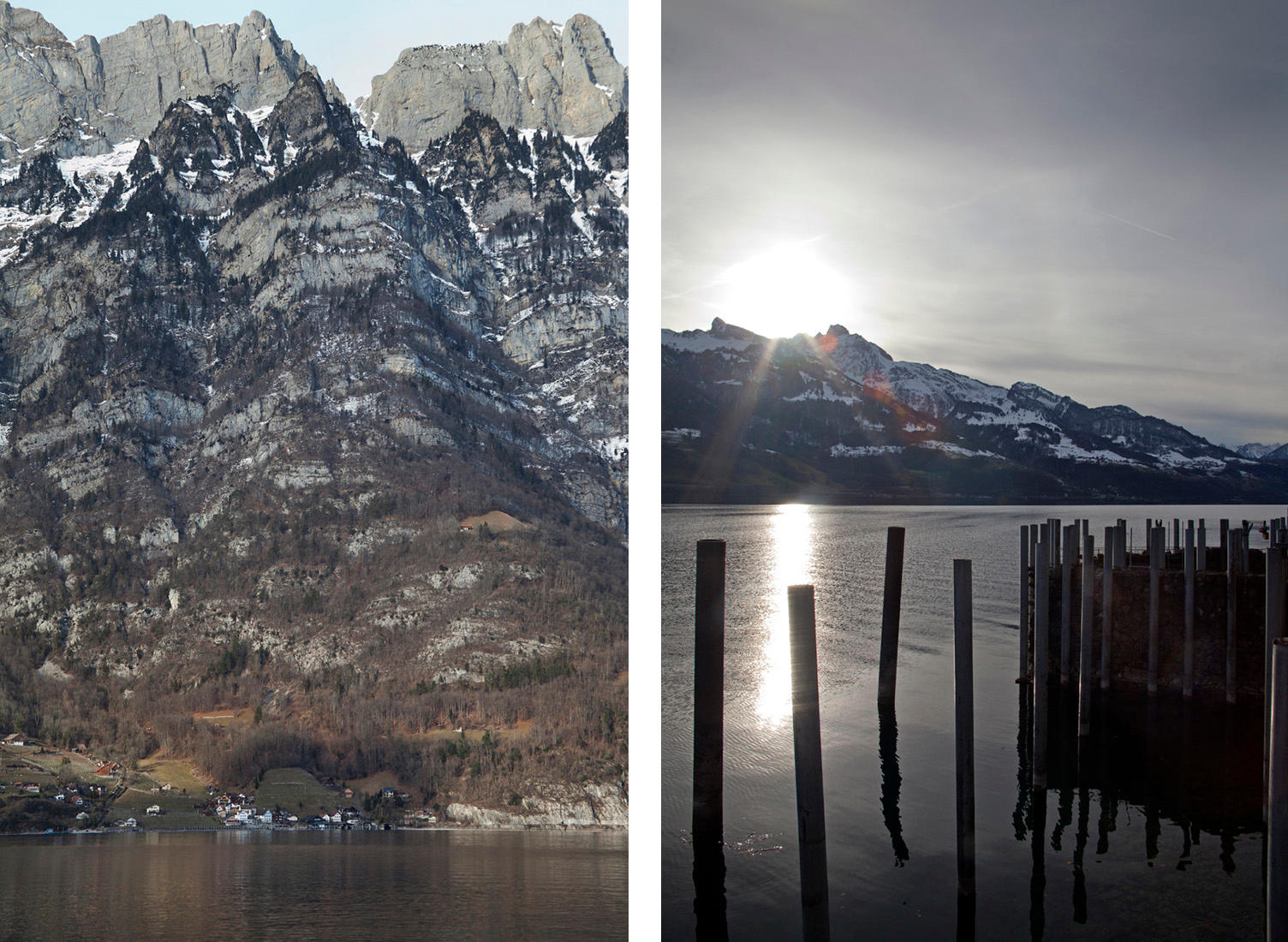




swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。